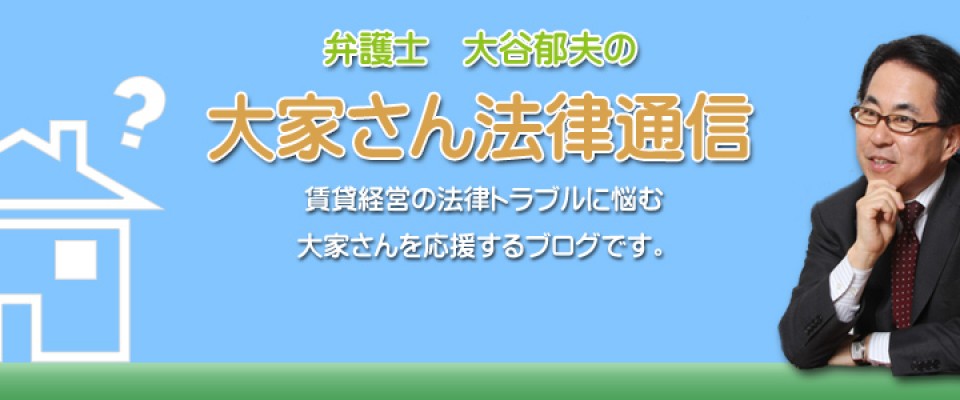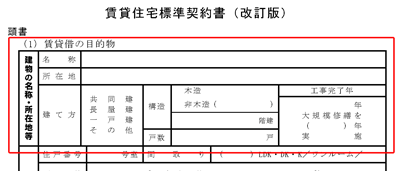他の仕事の関係で、3ヶ月ほどお休みしてしまいましたが、今週から大家さんの契約書教室を再開します。
今回は、契約書「頭書」(3)「賃料等」を見てみましょう。
よく「賃料」の欄に「共益費」の金額を合わせて書いてしまう大家さんがいます。たとえば、賃料が80,000円、共益費が6,000円であるとすると、賃料の欄に合計額の86,000円と書いてしまうのです。
しかし、この書き方はよくありません。賃料は、法律に定める手続きを踏まなければ値上げすることはできませんが、共益費は、きちんとした理由があれば、大家さんの側から、値上げをすることができます。たとえば、民間のゴミ回収業者や清掃業者を頼んでいる場合に、その業者の料金が値上げされた場合には、共益費の値上げを求めることができるのです。
ですから、「賃料」と「共益費」はきちんと分けて書くべきです。できれば、契約に際して、共益費の内訳も入居者に説明しておくと良いでしょう。
次に、「支払期限」の欄ですが、翌月分の賃料と共益費を当月末日までに払うというが普通ですから、翌月分に丸を付け、毎月「末」日まで と書くことになります。もちろん、末日ではなく、たとえば28日までがよいという場合は、入居者の了解を得て「28日」と書くこともできます。
「支払方法」の欄は、振込や自動振替の場合は、大家さんの預金口座を正確に書いてください。また、大家さんと入居者のどちらが振込手数料の負担するかについても、明記してください。
「敷金」の欄は、受け取った敷金が賃料の何ヶ月分で、合計いくらかを正確に書いてください。
「その他一時金」の欄は、例えば契約更新時に更新料を徴収する場合は、この欄に、「借主は契約更新時に更新料として新家賃の1ヶ月分を貸主に支払う。」と書いてください。これを書いておかないと、更新料を受け取れないおそれがあります。
「附属施設利用料」とは、(1)賃貸借の目的物の中の「付属施設」の利用料です。駐車場や駐輪場の使用料を賃料とは別に取る場合は、ここに記入してください。例えば、「駐輪場使用料 1ヶ月1台100円」というように、何を、どれだけの期間使用すると、いくらになるのかがはっきり分かるように書きましょう。ここに何も書いていないと、付属施設の利用料は請求できません。
最後に「その他」ですが、大家さんは契約書に記載のないお金は、原則として入居者に請求することができませんので、まだ書いていないもので、入居者に支払ってもらうものがあれば、必ず書いてください。
続きは次回に。。。